秋の特別展予告
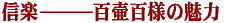
予告
|
秋の特別展予告
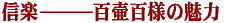 |
|
信楽は、古くは紫香楽とも書き、奈良時代、聖武天皇によって都が移され、大仏建立の詔が発せられた古い歴史をもつ地です。その後、都は奈良、平城京に移され、大仏開眼の法要は東大寺で盛大に営まれましたが、一時的にせよ、紫香楽は都となりました。その新京造営に際し、それに先立って建立された甲賀寺の屋根に瓦が用いられたことが、近年の発掘調査から明らかになりました。その瓦がどこで焼かれたか、つまり信楽の窯業の起源を奈良時代とするかどうかという問題は別にして、やがて信楽の地に窯業が起こったことは紛れもない事実です。
中世には常滑をはじめとして全国各地で窯業が盛んとなり、その中で特に盛んな窯業地を六古窯と呼んでいます。そのひとつに数えられる信楽は、中世諸窯の中では最も遅く起こり、常滑の影響を強く受けて窯業が本格化するのは13世紀末から14世紀初めにかけての鎌倉時代のこととされています。
中世信楽のやきものはいわゆる無釉の焼締め陶といわれるものです。
頑固な土が長時間炎にさらされる姿は「格闘」という言葉がふさわしく、そこから生まれた信楽のやきものは、まさに百壺百様、実に様々な表情をもっています。焼きただれたような焦げの肌、滝のように豪快に流れ落ちる目にも鮮やかな緑の自然釉、明暗濃淡とコントラスト豊かな火色の赤、風雨にたたかれ、冷え、枯れた野原を思わせる粗い土肌、プチプチとはじけるカニの目のような長石粒など、表現は人によって千差万別。信楽の見どころがいかに多いかということを物語っています。それは四季折々、それぞれに美しい大自然の姿と同じく、土と炎、自然が生み出した造形美といえるのではないでしょうか。
今回一堂に会する壺、甕、鉢は、海外からの里帰り8点や未発表作品を含む約180点余り。(予定)
中世信楽陶の魅力を存分にご堪能下さい。目の前の壺の景色が錦秋に彩られた信楽の山並みに、果ては銀河の星塊に見えてくるかもしれません。
|
 信楽桧垣文小壺
室町時代 15世紀 |
|
 信楽自然釉壺
室町時代 15世紀
|
||
 信楽自然釉大壺
室町時代 15世紀
|
||
|
||