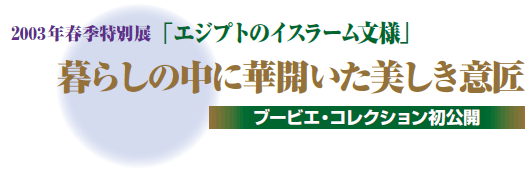 |
|
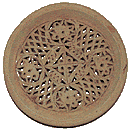 |
今度の展覧会のテーマは、飲み水を入れる素焼きの壷の首についていたフィルターの文様・・・何の事かちっともピンとこないでしょう。水を飲むときに見える、中の透かし彫りです。けれども実物を見ると、その愛らしさにびっくりしてしまいます。そしてなぜか私は、着物の半襟あるいは、裏地の朱を思い出したのです。
地味な普段着の襟足にもほのかな彩りを添える半襟は、豪華な着物や帯を装う以上にその人のおしゃれ心を伝えてきます。何気ない色合わせ、織の文様、布の光沢、その控えめさと同じ美しさを、フィルターに感じたのです。
フィルターはほとんどが、素焼きのままの白、あるいは赤い土色をしています。そこに表現されているのは、花びらや星、魚や象やらくだ、大きな目を見開いて見上げる子供、それから格子縞、同心円、組紐と、精緻な幾何学文様を取り入れながらも、なぜか肩のはらない、それどころか「ぷっ」と吹き出したくなるような文様ばかりです。
公式的にイスラームは、動植物の絵を描いたり彫刻することを禁じています。生き物を創造することは神の業なので、なまじ人間が真似をするのは好ましくないとの考えだそうです。ですからモスクの装飾には、具体的な花や動物、人間の姿などは、滅多に出てきません。そのかわりに、唐草文様や幾何学文様が、最高度に発達しました。文様の彼方には彼岸が続くのかと思うほど繊細高度です。けれども日常生活では、どうやら動物の愛らしさを捨て難かったのでしょう。エジプトの古都フスタートでは、この動植物を含むチャーミングなフィルターの文様を透かして、水を飲んでいたようです。
こんな遊び心を持った人たちは、いったい何をしながら、どんな色に囲まれて暮らしていたのでしょう。
|
 |
|
 |
|
 |
|

|
|
フスタートなど中世イスラームの都市に住む人たちは、様々な色や文様に囲まれていました。赤い絨毯、とりどりの陶器やガラス器、天井や壁は随所に凝った木彫と文様のペイント、中でも彼らが最も大切にしていたものは、光と風の効果ではないかと思います。
応接間は、暑い太陽を入れずに光や風を取り入れる工夫が凝らしてあります。天井の天窓から間接光を採り、張出し窓は細かい格子で、熱を遮りながら風を入れます。格子の上にはステンドグラスを嵌め、テーブルの足さえも透かし彫りにして、夜にはそこにランプを仕込むという徹底ぶりです。部屋の中央には、大理石モザイクで囲まれた噴水が涼しげです。
中東の猛暑の中で、水は貴重でした。何度も濾過して得た貴重な水を、素焼きの小さな壷に入れる、日陰で風の通る格子窓に置いておけば、気化熱ですっかり冷えた水が飲める、そんな楽しみをちょっぴり増すために、水壷のフィルターに細工をしたのでしょう。
このたびの展覧会では、彼らの日常生活を、併せてご紹介します。エジプトのオリエンタルな香りのサンプルも、どうぞお試し下さい。そしてフィルターや陶器や織物に見られる、繊細な文様感覚をご堪能下さい。
展示品の中でも、フィルターとコプト織で有名なブービエコレクションから、フィルター160点とコプト織14点が、この度日本で初公開となります。
|
 |
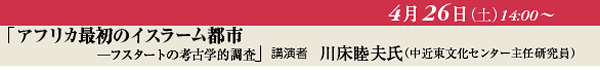 |
|
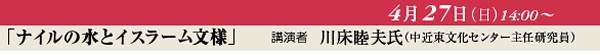 |
|
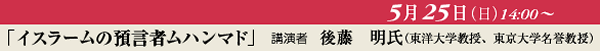 |
|