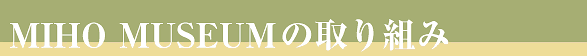
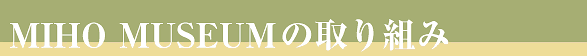 |
|
平成14年度より施行された『新学習指導要領』には、美術館を活用した鑑賞授業の必要性が明記され、学校と美術館との連携が大きく注目されています。
MIHO MUSEUM では、平成10年度より館内での子供向け教育プログラム(ストーリーテリングなど)を開始、翌11年度からは、小学校等への出張講座など館外での活動もスタートさせました。試行錯誤の中でのスタートでしたが、平成13年度には、第52回造形表現・図画工作・美術教育研究全国大会(滋賀大会 = 第50回滋賀県美術教育研究大会を兼ねる)へ、滋賀県立近代美術館、滋賀県立陶芸の森と共に参画、草津市の小学校にて参加した全国の先生方に対し公開授業を行いました。
そして、『新学習指導要領』が施行された平成14年度には、大津市のNPO「子供の美術教育をサポートする会」の仲介で、大津市立石山小学校の6,3,2,1年生、ほか4校に出張授業を実施しました。
本年度は、これらの活動を継続する一方で、教育現場の先生方にMIHO MUSEUM のこうした活動を知って頂き、また先生方の要望を聞かせて頂く機会を設け、より実践的で効果的な学校への協力や連携ができる態勢づくりを考えています。 |

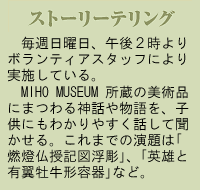
|
 |
「古代文明のなぞ」公開授業 ―アッシリアのレリーフからクサビ型文字を発見、 この文字でメッセージを書く― 学習中の平安時代から時間を遡って、日本の縄文時代と同じ頃にメソポタミアで作られた作品(アッシリアのレリーフ、前8世紀)の実物大図版を見て、石のレリーフに描かれている人物に思いをめぐらす。そして、レリーフ中にクサビ形文字を発見し、2800年前のメッセージが現在に伝えられていることを説明、子供たちに次の世代に残したいメッセージを考えてもらう。 |
|
| 実際に和楽器を目にし、また邦楽演奏を通して、美術館所蔵の滋賀県に縁のある雷雲蒔絵鼓胴の紹介へと導く。そして、自分たちがいま生活している郷土の歴史について学ぶ。 本物に触れることでその感動の種が将来大きく育まれ、また日本文化に触れることで、今後ますますボーダーレス化していく国際社会において、自国文化への誇りと異文化への理解に結びつけばと考える。 |
 写真:京都新聞提供 |
|