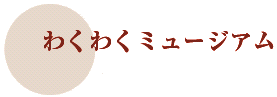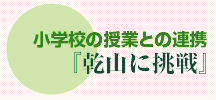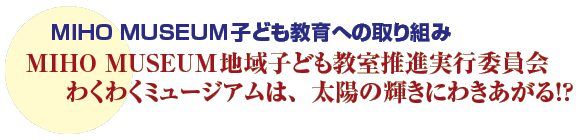
|
文部科学省が「未来の日本を創る心豊かでたくましい子どもを社会全体で育むため、学校(美術館・博物館)等を活用して、安全・安心な子どもたちの居場所(活動拠点)を設け、地域の大人を指導員として配置し、放課後や週末におけるスポーツや文化活動などの様々な体験活動や地域住民との交流活動等を支援する」。という趣旨を打ち出し、これを基にして、日本博物館協会内に、全国博物館における地域子ども教室推進事業運営協議会が設置されました。 そして、MIHO MUSEUM は、全国博物館における地域子ども教室推進事業運営協議会から再委託を受けて、MIHO MUSEUM 地域子ども教室推進実行委員会を発足しました。 2004年10月1日でした。名付けて、MIHO MUSEUM 地域子ども教室・わくわくミュージアム。 全12回行う予定で募集を掛けたところ、鰻登りに申し込みが増して、当初の定員、一回50名を大幅に上回ることになりました。結果は、総数934名のお申し込みをいただきました。 まず、「MIHO MUSEUM 地域子ども教室・わくわくミュージアム」(以下「わくわくミュージアム」)が、子どもたちの安全・安心な居場所として、心豊かでたくましい子どもを育むには、どのような事業を行えば良いか考えました。美術館でしか提供できないプログラムとは?やはり、当然のことですが、本物の美術品との出会いの場を、子どもたちに提供することでしょう。しかし、難しい論を振り回すことは避けねばなりません。それは、子どもの心が閉ざされてしまうからです。私たちは、まず、彼らの心の扉が開かれるように配慮しました。心が開かれれば、美術品からのメッセージが届くことでしょう。 それは、強い北風をおこして、無理矢理開かせたのではありませんでした。それでは、扉が壊れてしまう恐れがあります。反対に、暖かい太陽の光を当てたのです。すると、その太陽の光に誘われて、自然に扉は開かれるのです。 コーディネーターは、太陽の明るさで、出発の合図をします。「さあ、しゅっぱーつ!」 子どもたちは、首からミュージアム探検ワークシートをぶら下げて、「なんか、わくわくしてきたあ!」と顔を輝かせながら、後ろに付いて行きます。わくわくミュージアムの始まりでした。 あるNPOの代表者の方から、申し込みがありました。「うちは幼児が多くて、美術館内では、騒がしくするので、他の来館者に迷惑を掛けることが心配です。だから、館内には入らずに、建物の周辺で遊ばせるだけで結構です」という内容でした。しかし、「どのような幼児でも、彼らなりに美術品を楽しむことが可能です。大丈夫です!」と、わくわくミュージアムを勧めました。 この勧めに応じて、無事来館されました。幼児8人、小学生低学年3人、引率の大人は3人、合計14人でした。コーディネーターは、計画通りに、ご挨拶から太陽光線を放ち、出発。すでに子どもたちの心の扉は、開かれて、きらきらと光りだしているようでした。 ギャラリーに入り、子どもたちを、美術品の前で座らせました。それは、丁度、フランスのルーブル美術館で見た光景とそっくり。ローマのアポロンの彫像を鑑賞しつつ、アポロンとキューピットの物語を始めると、子どもたちのつぶらな瞳が大きく開かれて、瞬きを忘れたかのよう。そして、きらきらと輝き始めました。また、子どもたちを誘いながら、ギャラリーを回り、問いに答えたり、思い思いの感想を述べ合ったりしている間に、気が付けば、早2時間が経っていました。 帰りのバスの中でも、子どもたちは、美術館であったことを実に嬉しそうに話し合って、あっという間に時が過ぎました。 後日、このNPOの代表の方から電話が掛かりました。 「学級崩壊寸前のクラスに通う子どもの保護者の方から、相談を受けました。その方に、わくわくミュージアムを薦めておきました。あの場所に行くだけでも、心が癒されると思いましたから」と。 本事業を通して、多くの出会いが生まれました。 何よりも、多くの子どもたちの輝くような笑顔に出会えたことが、スタッフとして、この上ない喜びでした。 2004年12月、信楽公民館のクリスマス・イベントのお手伝いで出向した折、一人の小学生男児が、こちらを見るなり、指を差して、「あっ!ミホ・ミュージアムや!」と嬉しそうに大きな声を挙げました。こちらも、「あっ、彼は“遊楽スポーツ教室” の一員としてわくわくミュージアムに参加した子だ」と、即座に分かりました。彼は、“遊楽スポーツ教室”の後、家族を連れて、再度、わくわくミュージアムを体験していたのです。リピーターになった一人でした。家族を引き連れて来てくれた時は、あちらに何がある、こちらはこうだと、周囲の大人たちに説明をしてくれていました。立派なコーディネーター振りを発揮させていたのです。 このように、本事業は僅かな期間でしたが、確実に次世代の萌芽は芽吹き始めています。 この芽を摘み取ることなく、太陽の光と、充分な大自然の養分を与え続け、大樹へと育て、伸ばしてゆく事が本事業の使命だと思うのです。 MIHO MUSEUM は、山の美術館と呼ばれています。やはり、周辺には大樹がふさわしいでしょう。大樹があれば、泉も湧き、小鳥や獣も生き返ります。大自然が蘇ることができるのです。 学芸部 駒井 勉
|