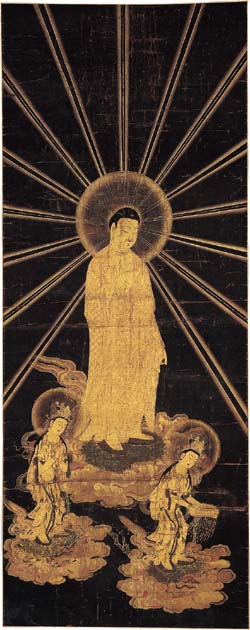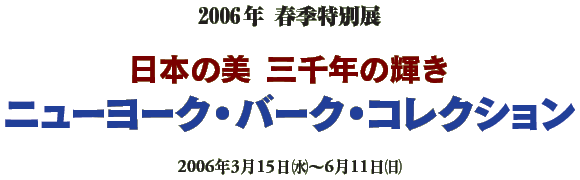
| 主催: | MIHO MUSEUM、京都新聞社、日本経済新聞社、バーク・コレクション |
| 後援: | アメリカ大使館、滋賀県、滋賀県教育委員会、NHK大津放送局、びわ湖放送株式会社 |
| 協賛: | 伊藤忠商事、NEC |
| 協力: | 日本航空 |
昨年7月に岐阜会場から始まり、広島、東京会場を経て、いよいよ3月15日から「日本の美 三千年の輝き ニューヨーク・バーク・コレクション展」が MIHO MUSEUM で開催されます。昭和60年に初めて日本でバーク・コレクションが紹介されてから、このたびの展覧はちょうど20年ぶりとなります。