| 舎利容器とは、お釈迦様の舎利を奉安するための容器で、寺院の中心となる塔の礎石に、舎利は様々な宝物と共に安置されました。7世紀に天智天皇が国の守りとして崇福寺を建立された時も立派な塔が建ちましたが、こんな伝説が今に伝わっています。 ある晩、天皇の夢に法師が現れました。北西の山を見なさいとのお告げに驚いて山を眺めると、火が細く昇って30mもの高さに光っています。不思議に思った天皇は、その山に寺を建てることを決め、やがて巨大な寺院―崇福寺を建立しました。 その崇福寺の塔跡とされる場所から出土したのが、写真の舎利容器です。大切な舎利を奉安する容器として金、銀、銅そしてガラスの器が選ばれています。四重容器の一番内側に緑瑠璃壺−緑ガラスの壺が使われたということは、ガラスが金・銀・銅よりも貴重だったことを示しています。 |
 |
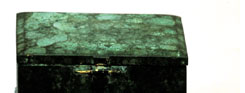 |
|
 |
|
 |
|||||
| 会期 | 2006年7月15日(土)〜8月20日(日) | ||||
|
|||||
ガラスがまるでカーテンのようにたなびくのは、あおい貝をかたどった花生です。大きさといいデザインといい、びいどろの器の中でも最高傑作のひとつでしょう。一方、無色透明なガラスはぎやまんと呼ばれ、より高級なものでした。切子を施されたぎやまんの器には、イギリスやアイルランドのデザインが取り入れられましたが、その切子の線は、金属製の棒状工具で、職人が一本一本刻んでいったものでした。和ガラスの歴史を辿りながら、切子の柔らかな光と線、びいどろの高雅な意匠を、どうぞお楽しみ下さい。
