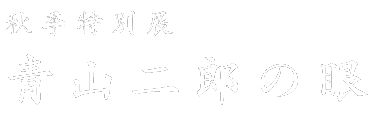
会期 2006年9月1日(金)〜12月17日(日)
| 主催 | MIHO MUSEUM、読売新聞社 |
| 後援 | 滋賀県、滋賀県教育委員会、NHK大津放送局、びわ湖放送株式会社 |
| 協力 | 新潮社 |
| 監修 | 青柳恵介 |
| 企画協力 | 株式会社ジパング |
小林秀雄、白洲正子の骨董の師匠でもあった青山二郎の初の特別展。「青山二郎の眼」では、その眼に適った中国(東京国立博物館・横河コレクション)・朝鮮・日本の古陶磁の逸品を中心に、彼及びゆかりの人々の旧蔵品、手がけた装幀作品などを通して、伝説の人物である青山二郎の眼にせまります。
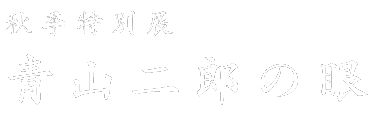 会期 2006年9月1日(金)〜12月17日(日) |
|||||||||||
小林秀雄、白洲正子の骨董の師匠でもあった青山二郎の初の特別展。「青山二郎の眼」では、その眼に適った中国(東京国立博物館・横河コレクション)・朝鮮・日本の古陶磁の逸品を中心に、彼及びゆかりの人々の旧蔵品、手がけた装幀作品などを通して、伝説の人物である青山二郎の眼にせまります。 |
|||||||||||
| 白洲正子の物語も、小林秀雄の骨董も、この男からはじまった。 | |||||||||||
|
『人間でも、陶器でも、たしかに魂は見えないところにかくれているが、もしほんとうに存在するものならば、それは形の上に現れずにはおかない。それが青山二郎の信仰であった』(「いまなぜ青山二郎なのか」)と白洲正子は青山を評した。『青山さんが偉いのは、「写真で見れば解る」鑑賞陶器から、「写真で見ても解らない」陶器の真髄、いわば形の中にある魂を求めたことにある』(「いまなぜ青山二郎なのか」)と。
また、小林秀雄は戦前戦後をはさんで、青山とともに骨董の魂を見出すことに精力を注いで、文体に生命力を持つに到る。小林は井伏鱒二に、骨董に夢中になっていたおかげで「文学が分かるようになったよ」ともらし、戦後の座談で「美は真を貫く、善もつらぬくかもしれない」と語り、人生や文学に与える美の力を自らの筆の力で世に証明していった。 十代半ばで中国陶磁器の逸品を買い、二十代にして鑑賞陶器、民芸運動、李朝工藝の総ての初動に立ち会い、豪華写真集を刊行し、現代まで続く陶磁器愛好の流れを期せずしてプロデュースした男。小林秀雄をはじめ河上徹太郎、永井龍男、中原中也、大岡昇平、今日出海等、昭和の文壇史を彩るメンバーが集結した通称「青山学院」の校長であり、小林に「僕たちは秀才だがあいつだけは天才だ」と言わしめた「眼」。自ら文章を書く傍ら、生涯に2000点に及ぶ装幀作品を手掛けた自称「人情装幀家」・・・・。 |