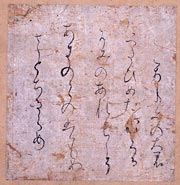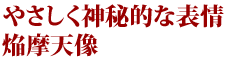

重要文化財
えんまてんぞう
焔摩天像
焔摩天像
平安時代(12世紀)
絹本著色 縦155.8cm 横84.5cm
この焔摩天像は明治の大コレクター原三渓の旧蔵。平安時代12世紀頃に描かれましたが、美しい色が驚くほどよく残り、当時の仏教に内在した美を今日に遺憾なく伝えています。これは除病、延命、息災を祈る焔摩天法という密教の修法の本尊だったと考えられています。画像の前に壇を設け、定められた法に則って修法することにより、祭主を脅かす目に見えない存在を、焔摩天の威力で退散させようとしたのです。
もっとも焔摩天そのものは、釈迦よりも古い歴史をもちます。もともとインド古代神話のヤマという神で、太陽神ヴィバスバットの息子として生まれました。彼は人々の為に冥界へと旅立ち、人類最初の死者となって死者の安住する楽土を発見し、冥界の王となったとされます。後にヤマは死者を裁く役割を与えられ、冥界も地獄のイメージを合わせ持つようになりました。
この画像では、やさしく神秘的な表情、ふくよかな肢体に朱みがさし、何気ない牛の眼差しにも古い知恵が宿っているかのような力が感じられます。
焔摩天像の展示期間は11月3日(火)から11月8日(日)までの6日間。
もっとも焔摩天そのものは、釈迦よりも古い歴史をもちます。もともとインド古代神話のヤマという神で、太陽神ヴィバスバットの息子として生まれました。彼は人々の為に冥界へと旅立ち、人類最初の死者となって死者の安住する楽土を発見し、冥界の王となったとされます。後にヤマは死者を裁く役割を与えられ、冥界も地獄のイメージを合わせ持つようになりました。
この画像では、やさしく神秘的な表情、ふくよかな肢体に朱みがさし、何気ない牛の眼差しにも古い知恵が宿っているかのような力が感じられます。
焔摩天像の展示期間は11月3日(火)から11月8日(日)までの6日間。