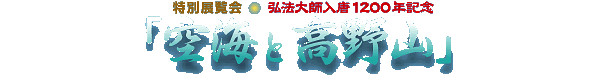
主 催: |
京都国立博物館/高野山真言宗総本山金剛峯寺/財団法人高野山文化財保存会/NHK京都放送局/NHKきんきメディアプラン |
会 期: |
2003年4月15日(火)〜5月25日(日) |
観覧時間: |
午前9時30分〜午後6時(毎週金曜日は午後8時まで、いずれも入館は閉館時間の30分前まで) |
休 館 日 : |
4月21日(月)、5月6日(火)、5月12日(月)、5月19日(月) |
会 場: |
京都国立博物館・本館全室 |
| 京都国立博物館の春の特別展覧会は、「霊峰(おやま)がまるごと降(お)りてきた!」というコピーのもと、高野山一山の文化財が一堂に会するという本当に豪華な展覧会です。これは、弘法大師空海(774〜835)が延暦23年(804)、真言密教の教えを求めて中国に旅立った「入唐求法(にっとうぐほう)」から、1200年の節目を迎えることを記念して開催されるものです。 |
| この展覧会は、「空海と高野山の歴史」「空海の思想と密教のかたち」「信仰の重なりとその美術」「山の正倉院」「近世の高野山」という5テーマを設けていますが、今回の目玉の一つが国宝「聾瞽指帰(ろうこしいき)」、国宝「諸尊仏龕(しょそんぶつがん)」、重文「飛行三鈷杵(ひぎょうさんこしょ)」という空海ゆかりの「高野山三大秘宝」が同時に公開されるというものです。これは初めての出来事です。 |
| 国宝「聾瞽指帰」は、若き空海の自筆。延暦16年(797)、24歳の時に撰述した著作であり、その内容は、儒教・道教・仏教の各々を信ずる三人を登場させ、それぞれの信ずるところを述べさせながら、最後には前二者が仏教の教えに深く感服するというものです。 四六駢儷体(しろくべんれいたい)を駆使して戯曲風に綴られた文章は、入唐前の空海の文才と習学ぶりを遺憾なく発揮しています。ことに注目すべきは、全巻にわたって筆法に工夫が凝らされていることであり、なかでも下巻に収められている「観無常賦(むじょうをかんずるのふ)」や「生死海賦(しょうじかいのふ)」そして全体を締めくくる「十韻詩(じゅういんのし)」などの筆致がすばらしい。料紙には所謂「縦簾紙(じゅうれんし)」が用いられており、漢字文化圏における書跡の名品の一つといっても過言ではありません。 |
| 国宝「諸尊仏龕」は、空海が中国から持ち帰ったもので、高さが約23cmという小型の厨子(ずし)。キャビネット状で前面を左右に開く構造になっており、その昔は白檀の香りが漂ったに違いありません。三尊形式で、そのまわりを菩薩・比丘・金剛力士などが囲繞(いにょう)しており、全体が細密な高肉彫で彫り出されています。インド僧金剛智・不空三蔵、そして空海の師である恵果阿闍梨(けいかあじゃり)と伝わり、それを空海が恵果阿闍梨から伝授されたものと云われ、三国伝来の重宝として尊ばれているものです。 |
| 重文「飛行三鈷杵」は、空海が中国からの帰国に際し、密教流布の地を選ばんとして中国・明州より投げたとされるもの。これが高野山の松に引掛かったとされ、世にいう「飛行三鈷」の伝説が生まれたのです。高野山開創に関わったとされる重要な遺品というべきもので、これが公開される機会はほとんどありません。因みに三鈷杵は、密教法具の一つで、両端が三つに分岐した金剛杵、魔を砕くという。 |
| これら以外には、絵画では仏画の二大傑作である国宝「仏涅槃図」(4/15〜5/5)・国宝「阿弥陀聖衆来迎図」(5/7〜5/25)、近世では池大雅筆の襖絵である国宝「山水人物図」10面のうち4面、彫刻では補作2躯を含む8躯すべてが展示される運慶作の国宝「八大童子像」、快慶作の重文「孔雀明王像」、書跡では中尊寺経として知られる国宝「金銀字一切経」、高野山の文書を集めた国宝「宝簡集」の中から源頼朝書状などがあります。工芸品では、密教法具は云うに及ばず、伝法灌頂に用いられる「秘密儀式灌頂法具」や国宝「澤千鳥螺鈿蒔絵小唐櫃」などがあります。その他、「霊峰がまるごと降りてきた!」だけあって、仏教美術を中心とした名品が目白押しです。 |
| 尚、この展覧会は終了後、今秋に愛知県美術館、来春に東京国立博物館、その秋に和歌山県立博物館に巡回しますが、当館での総作品数は154件、そのうち国宝が21件、重文が101件というまさにオールスターが大集結した空前絶後の展覧会と云ってもよいでしょう。ぜひ、この機会をお見逃しなく! |
| (京都国立博物館・保存修理指導室長・赤尾栄慶(あかお えいけい)) |