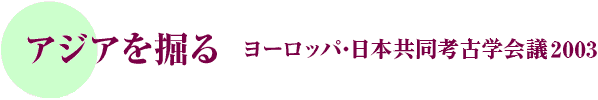 |
|
昨年12月11日(京都市会場・関西日仏学館)と12日(滋賀県会場・MIHO MUSEUM)、2003年ヨーロッパ・日本共同考古学会議「アジアを掘る」が開催された。2日目の会場となったMIHO MUSEUM では、アフガニスタン、イラン、シリア、カンボジア、中国などアジアの各地で活動する考古学者が集まり、発掘や保存活動の現場を取り巻く問題点について討論した。
|
 |
そして、発掘の成果ばかりでなく、フィールドワークにおける技術的なノウハウや分析方法と理論など、考古学調査研究に関する多くの知識、情報を共有すべく、ヨーロッパ―日本間の恒久的な連絡委員会を創設し永続的な協力関係を築く事を確認した。次回の共同会議は、2005年末に開催される予定である。 |
|
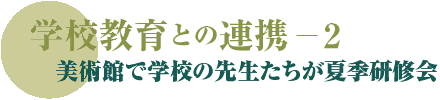 |
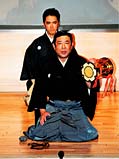 能楽演奏を鑑賞 |
||||||
昨年8月11日、12日と「平成15年度 美術館からの発信“日本の宝物に出会う−総合的学習を美術館と共に”」が、滋賀県立陶芸の森とMIHO MUSEUM の主催で、両館を会場に開かれた。コーディネーターには世田谷美術館・学芸員高橋直裕さんを招き、美術館関係者と学校教員約130名が両美術館のワークショップを体験した。
|
|||||||
|
初日の会場となったMIHO MUSEUM では、午前中グループに分かれて展示室を回り、クイズ形式で「美術館の謎」を解くミュージアムオリエンテーリングを体験した。「絵の中の動物の数」や「親指を上げていたのはどちらの手か」など予想もしない問題に参加者たちは拍手や歓声を上げていた。 午後はMIHO MUSEUM がこれまで草津市内のいくつかの小学校で行った授業を基にしたプログラム「本物に触れる:歴史の裏舞台から」を体験した。まず能楽のシテ、笛、小鼓など、それぞれの和楽器の説明と実際の演奏を鑑賞、その楽器のひとつ「鼓」にスポットをあてる。そしてMIHO MUSEUM の所蔵品である「信長の書状と雷雲蒔絵鼓胴」のレプリカを使って学芸員と共に書状を読み解き、そこに登場する雷雲蒔絵鼓胴を実際に見ることで、書状に書かれている事実を確かめるという美術館ならではの醍醐味を味わった。 2日目は滋賀県立陶芸の森において陶芸についてのワークショップと「パネルディスカッション?美術館と体験学習」が行われ、この研修とこれまでの美術館と学校との連携授業を振り返った。 今回の研修会では、美術館でできるワークショップを体験していただき、美術館の魅力をまず学校の先生方に感じてもらえたこと、また美術館と学校、美術館同士がお互い一歩ずつ近づけたことが大きな収穫となったように思う。 |
|||||||
|
|||||||