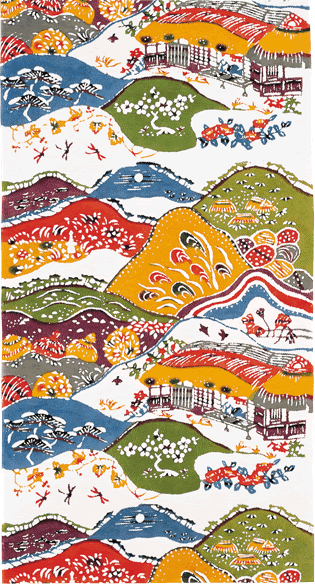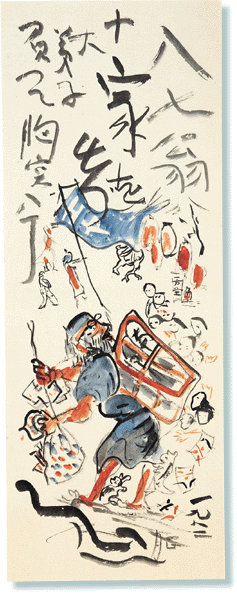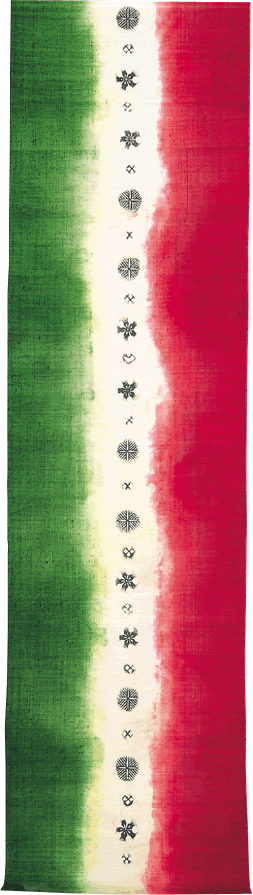
染分け小花文帯地
1960年頃
津村小庵文帯地
1967年
1967年
「花は紅、柳は緑」この単純な真実が、赤絵の魅力の原点だと思う。芹沢先生の文様があれほどバラエティーに富みながら、どれも胸の奥まで響いて来るのは、この真実にしっかりと軸足をおかれていたせいではなかろうか。
「いつもの事ながら 赤絵を想ふと 模様が出てくる」
「沖縄から、九州、大阪、東京へと、道すがら地べたに筵を敷いて、赤絵を売って歩こうか。」
芹沢先生は巡礼の旅に出たいと、よく話しておられたという。その旅に着て行く衣装も決まっていたのだとか。