
図4
つぎに、幾つかの出品作品から飛鳥仏の面影をひろってみましょう。

博興県出土の菩薩像(表紙、裏表紙参照)は両肩に懸かる先端がカールする垂髪、腹前でX字状に交差する天衣、下腹をすこし前に突き出すように立つ姿勢など、北魏後期の様式を基本としており、秀でた眉とややつり上がったアーモンド形の眼や、アルカイックスマイルをたたえる口元には法隆寺の救世観音像にも通じる気品を湛えています。

山東省博物館所蔵の北斉時代、天保七年(556)の銘をもった銅製鍍金・釈迦三尊像(図4)は、小像ながら、大きな舟形の光背に三尊を並んで表しており、仏菩薩の着衣の裾や天衣の端が左右に強い張りを見せる形状、品字形の衣文など、法隆寺金堂の釈迦三尊像と共通する特色をもっています。

安丘市博物館所蔵の菩薩立像(図5)の足元に残る力士の頭部は、推古天皇の20年(612)に百済の帰化人味摩之によって伝えられたという伎楽の面・金剛(法隆寺献納宝物)を彷彿させます。
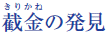

さらに、青州市龍興寺跡から出土した北斉時代の菩薩像残欠の飾り帯には二重の亀甲繋ぎの中に亀の文様がひしめくように表現されており(図6)、これらが金箔を細く切って貼り付ける截金(きりかね)の技法で作られていることから、これも法隆寺の玉虫厨子や金堂の四天王像に見られる技法の起源が中国に現存していたことを確認させる発見となりました。

なお、蝉の冠飾りを着けた三体の菩薩像は、特別展終了後2007年12月までMIHO MUSEUM で公開されます。
博興県出土の菩薩像(表紙、裏表紙参照)は両肩に懸かる先端がカールする垂髪、腹前でX字状に交差する天衣、下腹をすこし前に突き出すように立つ姿勢など、北魏後期の様式を基本としており、秀でた眉とややつり上がったアーモンド形の眼や、アルカイックスマイルをたたえる口元には法隆寺の救世観音像にも通じる気品を湛えています。
山東省博物館所蔵の北斉時代、天保七年(556)の銘をもった銅製鍍金・釈迦三尊像(図4)は、小像ながら、大きな舟形の光背に三尊を並んで表しており、仏菩薩の着衣の裾や天衣の端が左右に強い張りを見せる形状、品字形の衣文など、法隆寺金堂の釈迦三尊像と共通する特色をもっています。
安丘市博物館所蔵の菩薩立像(図5)の足元に残る力士の頭部は、推古天皇の20年(612)に百済の帰化人味摩之によって伝えられたという伎楽の面・金剛(法隆寺献納宝物)を彷彿させます。
さらに、青州市龍興寺跡から出土した北斉時代の菩薩像残欠の飾り帯には二重の亀甲繋ぎの中に亀の文様がひしめくように表現されており(図6)、これらが金箔を細く切って貼り付ける截金(きりかね)の技法で作られていることから、これも法隆寺の玉虫厨子や金堂の四天王像に見られる技法の起源が中国に現存していたことを確認させる発見となりました。
なお、蝉の冠飾りを着けた三体の菩薩像は、特別展終了後2007年12月までMIHO MUSEUM で公開されます。
| 作品データ |
|
| 表紙 | 菩薩立像 北魏-東魏時代 山東省蔵 |
| 図1 | 釈迦三尊像(部分)東魏時代 天平3年(536)青州博物館蔵 |
| 図2 | 蝉文金飾 東晋時代4 ~ 5世紀 南京仙鶴観高崧家族墓出土 南京市博物館蔵 |
| 図3 | 菩薩立像 東魏時代 青州市博物館蔵 |
| 図4 | 仏三尊像 北斉時代 天保7年(556) 山東省博物館蔵 |
| 図5 | 菩薩立像(部分) 北斉時代 安丘市博物館蔵 |
| 図6 | 菩薩像残欠(部分) 北斉時代 青州市博物館蔵 |
| 図7 | 菩薩立像 北斉時代 青州市博物館蔵 |
写真撮影 山崎兼慈 |
|

図5

図6

図7