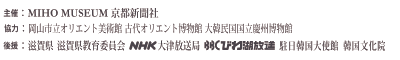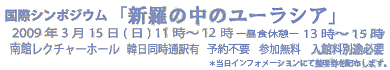象嵌瑠璃首飾
五-六世紀

左の首飾は慶州の味鄒王陵地区から発見されました。紺碧ガラス・瑪瑙・水晶の珠、青玉管、瑪瑙の勾玉で構成され、要部分にモザイクガラスを象嵌したガラス珠がつけられています。この珠には人物の顔面と白い鳥、そして花をつける小枝文が象嵌されています。この珠がどこでつくられたのかは説が分かれていますが、これらの顔面は碧眼で眉がつながり、冠を頂き、魅力的な微笑みをたたえています。
五-六世紀
左の首飾は慶州の味鄒王陵地区から発見されました。紺碧ガラス・瑪瑙・水晶の珠、青玉管、瑪瑙の勾玉で構成され、要部分にモザイクガラスを象嵌したガラス珠がつけられています。この珠には人物の顔面と白い鳥、そして花をつける小枝文が象嵌されています。この珠がどこでつくられたのかは説が分かれていますが、これらの顔面は碧眼で眉がつながり、冠を頂き、魅力的な微笑みをたたえています。
角杯形土器
慶州 味鄒王陵
五-六世紀

東アジアに角杯が出現したのは古代王朝が滅び次の王朝へと移行する変動の時代でした。この時期に草原遊牧民との交流が活発になり、スキタイ系の角杯の風習が入ってきたのでしょう。韓半島では三国時代にこれが見られます。角杯の発掘例は新羅の都慶州を中心に分布しています。
慶州 味鄒王陵
五-六世紀
東アジアに角杯が出現したのは古代王朝が滅び次の王朝へと移行する変動の時代でした。この時期に草原遊牧民との交流が活発になり、スキタイ系の角杯の風習が入ってきたのでしょう。韓半島では三国時代にこれが見られます。角杯の発掘例は新羅の都慶州を中心に分布しています。




銀製杯 皇南大塚 五世紀

この銀杯の表面には新羅の金属工芸にしばしば見られる天体をつなぐかのような亀甲文が施され、中に瑞獣などが配されています。このような意匠は東アジア遊牧民の馬具などに見られる意匠と共通するものがあり、古墳時代の日本にももたらされました。
この銀杯の表面には新羅の金属工芸にしばしば見られる天体をつなぐかのような亀甲文が施され、中に瑞獣などが配されています。このような意匠は東アジア遊牧民の馬具などに見られる意匠と共通するものがあり、古墳時代の日本にももたらされました。
亀甲文杯 (左)慶州天馬塚出土 六世紀
(右)イラン 三-四世紀

左の青い瑠璃杯は慶州の天馬塚から出土したもので、右のイラン由来の瑠璃杯と大変良く似ています。底に亀甲、側面に線条を刻んだ、浅い円柱状の型にガラスを吹き込み、型からはずして宙吹きして成形したようです。類例は東地中海から南ロシア周辺に見られますが、左の瑠璃杯は東アジアでは唯一の出土例です。その原型はローマの切子ガラス器にあり、おそらく手軽に量産するために開発された手法だったのでしょう。
(右)イラン 三-四世紀
左の青い瑠璃杯は慶州の天馬塚から出土したもので、右のイラン由来の瑠璃杯と大変良く似ています。底に亀甲、側面に線条を刻んだ、浅い円柱状の型にガラスを吹き込み、型からはずして宙吹きして成形したようです。類例は東地中海から南ロシア周辺に見られますが、左の瑠璃杯は東アジアでは唯一の出土例です。その原型はローマの切子ガラス器にあり、おそらく手軽に量産するために開発された手法だったのでしょう。