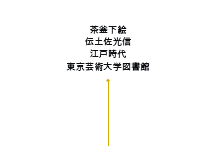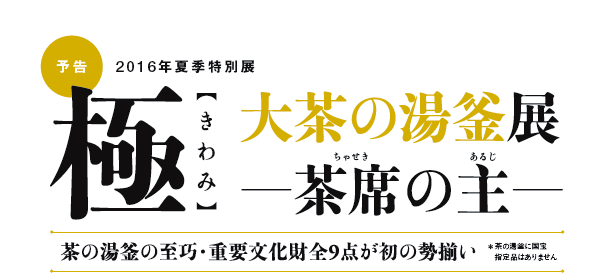




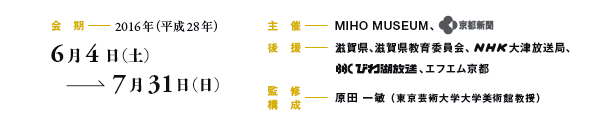

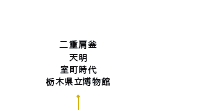

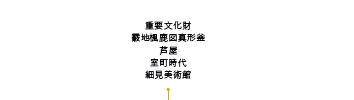



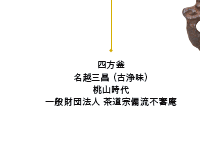


変化し、茶人の審美眼に叶うように形づくられてゆきます。
本展は“茶の湯釜”の研究者である原田一敏先生(東京芸術大学大学美術館教授)の監修により構成され、芦屋釜・天明釜に加え与次郎釜など初期京釜、江戸時代の釜にも焦点を当て、その代表作を中心に、奈良時代から近世までの釜の歴史とその美を展望しようとするものです。また、“茶の湯釜”は(国宝は無く)重要文化財が9点指定されていますが、本展はその全作品が初めて一堂に会す画期的な展観となります。この機会をどうぞお見逃しなく。
本展は“茶の湯釜”の研究者である原田一敏先生(東京芸術大学大学美術館教授)の監修により構成され、芦屋釜・天明釜に加え与次郎釜など初期京釜、江戸時代の釜にも焦点を当て、その代表作を中心に、奈良時代から近世までの釜の歴史とその美を展望しようとするものです。また、“茶の湯釜”は(国宝は無く)重要文化財が9点指定されていますが、本展はその全作品が初めて一堂に会す画期的な展観となります。この機会をどうぞお見逃しなく。