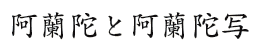

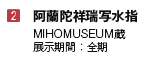
磁器を目指しながら陶器を脱することができなかったデルフト陶が、むしろ、日本人の美意識に適ったのでしょうか。江戸時代に日本へ入ってきた作品は大切に伝世してきました。

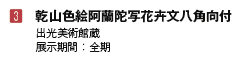
陶工・尾形乾山の鳴滝時代、様々な試みの中で生まれた阿蘭陀写は、単なる写しを超えたオリジナリティーと完成度の高さを持っていました。
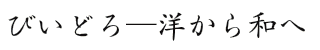
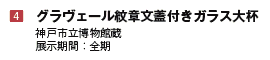
オランダ語で「ボカール(Bokaal)」、ドイツでは「ポカール(Pokal)」と呼ばれる脚付きで蓋をともなう酒杯です。当時、ヨーロッパ製ガラス器は、希少な贈答品として珍重されていました。


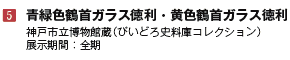
こうした鶴首徳利は、長崎で1670年代には造られていたと推定され、遅くとも18世紀初期には大阪に製法が伝播し、やがて江戸でも製作されるようになります。ヨーロッパのガラスに倣いながらも、日本の風土に合った和ガラスを生みだした当時の技術と美意識に驚かされます。