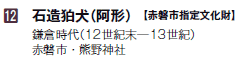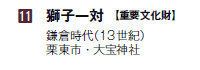
平安時代の中期から後期、南都の名刹、薬師寺に伝えられる一対(重要文化財)は、寛治元年(1087)に作られたもので、王朝の優雅さを伝える気品の高さは感動的である。最近、重要文化財に指定された、岡山県津山市の高野神社に伝えられた二対のうちの一対は、ユーモアを感じさせる茫洋とした出来栄えで、その穏やかな典雅さは、定朝様などの仏像にも通じるところがある。山陽道には優れた作例が伝えられているが、広島県三原市の御調八幡宮に伝わる一対(重要文化財)は、まことに堂々とした像。御調八幡宮からは、重要文化財に指定される、とてつもなく大きい獅子頭も出品して頂く。また、海外に流出した迫力満点の作品も出品される。(図10)
鎌倉時代になると、筋肉質で精悍な作例が作られる。霊場白山に関わる、奥美濃長瀧神社の狛犬は有名な作品である。滋賀県にも多くの優れた像が伝えられているが、完成度の高さからすると、栗東市・大宝神社の一対(重要文化財)であろう。その高貴な威圧感は、単なる守護獣の域を大きく飛び越えている。また、草津市・志那神社、湖東三山のひとつ金剛輪寺、湖北の長浜市・白髭神社などにも、素晴しい鎌倉時代から南北朝時代の狛犬が残されている。鎌倉時代は、日宋貿易によって、多くの文物が大陸の宋から請来されるが、東大寺の再建に尽力した俊乗坊重源が関与するとみられる岡山県赤磐市・熊野神社に伝えられる異国風の獅子もまことに興味深い像である。
鎌倉時代になると、筋肉質で精悍な作例が作られる。霊場白山に関わる、奥美濃長瀧神社の狛犬は有名な作品である。滋賀県にも多くの優れた像が伝えられているが、完成度の高さからすると、栗東市・大宝神社の一対(重要文化財)であろう。その高貴な威圧感は、単なる守護獣の域を大きく飛び越えている。また、草津市・志那神社、湖東三山のひとつ金剛輪寺、湖北の長浜市・白髭神社などにも、素晴しい鎌倉時代から南北朝時代の狛犬が残されている。鎌倉時代は、日宋貿易によって、多くの文物が大陸の宋から請来されるが、東大寺の再建に尽力した俊乗坊重源が関与するとみられる岡山県赤磐市・熊野神社に伝えられる異国風の獅子もまことに興味深い像である。
室町時代、桃山時代と時代が進むに連れ、伝統を継承しながらも、各地に個性的な狛犬が現れる。焼き物の産地の瀬戸では、陶器の狛犬が作られ、比較的簡素な作りの石造品も現れる。奥州の奸雄として知られる戦国大名の最上義光の名がみえる銅造の狛犬も、興味深い逸品である。江戸時代、全国を遊行して多くの像を生みだした円空が彫った個性的な狛犬は、岐阜県・高賀神社に祀られ、いまも篤い信仰を集めている。
ほんの一部を紹介したこれらの貴重な獅子・狛犬は、文化財保存の観点から展示替えされながら、MIHO MUSEUM へ集合する予定である。ユーラシア大陸を長途して日本列島に至った聖獣は、独特の役割を担わされ、そして我が国の人々に、今も愛されているのである。
ほんの一部を紹介したこれらの貴重な獅子・狛犬は、文化財保存の観点から展示替えされながら、MIHO MUSEUM へ集合する予定である。ユーラシア大陸を長途して日本列島に至った聖獣は、独特の役割を担わされ、そして我が国の人々に、今も愛されているのである。