
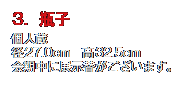
瓶子は神に献酒するための神饌具と考えられ、通常は一対で神前に供えられました。現在では諸家に分蔵されている瓶子が、本来の一対の形で展示されるのも、本展覧会の見どころの一つです。
この瓶子は、残念ながら一口しか現存していませんが、その堂々たる姿と存在感は他を圧倒しています。注口からの外向きの曲線、底部からの内向きの曲線が明確に肩の部分で区分されるこの形式は、瓶子の中でも和様を示すものと考えられています。
この瓶子は、残念ながら一口しか現存していませんが、その堂々たる姿と存在感は他を圧倒しています。注口からの外向きの曲線、底部からの内向きの曲線が明確に肩の部分で区分されるこの形式は、瓶子の中でも和様を示すものと考えられています。
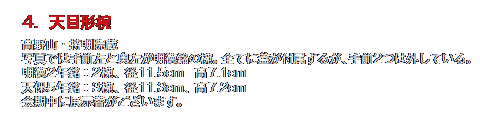
底部に年紀のある珍しい木製の天目椀で、今まで東京国立博物館所蔵の1点のみが知られていました。今回、高野山霊宝館様のご協力で新たに2椀が見出されました。
おもしろいことに、明徳2年(1391)の年紀が入るこの天目椀2客に、江戸時代の京都の漆匠、佐野長寛(1794−1856)が天保5年(1834)に3椀を補造して5客とし、さらに蓋をつくり菓子椀として伝来していたのです。
5客の色がそろっていることから、長寛による古椀の塗り直しの可能性も考えられますが、天目茶碗を写して作られた椀が江戸時代に再利用されていた事実も伝えてくれる貴重な例といえます。
おもしろいことに、明徳2年(1391)の年紀が入るこの天目椀2客に、江戸時代の京都の漆匠、佐野長寛(1794−1856)が天保5年(1834)に3椀を補造して5客とし、さらに蓋をつくり菓子椀として伝来していたのです。
5客の色がそろっていることから、長寛による古椀の塗り直しの可能性も考えられますが、天目茶碗を写して作られた椀が江戸時代に再利用されていた事実も伝えてくれる貴重な例といえます。
